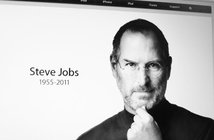消費税の増税は延期以外にありません。いまの日本は、北欧などと比べて生活の最低保証部分が少ないぶん消費税の影響が大きく、ストレートに貧困化に繋がるからです。(『ニューヨーク1本勝負、きょうのニュースはコレ!』児島康孝)
現状は厳しい日本経済、しかし若手正社員は一足先に景気上昇中
これからの景気はバブル的に上昇へ
日本経済は、長いデフレから反転し始めています。
現状の理解は、マクドナルドが格安のハンバーガーを販売した時期、今から10年~15年前を考えるとわかります。
あの当時、ハンバーガーなどの価格が下がって、消費者には「朗報」でした。
価格破壊という言葉が流行り、モノが安く買えるということで歓迎ムードさえありました。
当初は、賃金のデフレが時間差を置いて進む前でしたから、時間差が機能して良い面だけが出ていたのです。
現在は、まさにこの反対です。
デフレから脱却する当初は、あまり景気が良くなくて、賃金や雇用もなかなか良くなりません。
物価の上昇が、一部、先行もするでしょう。
収入が増えない中での物価上昇は「悲報」です。
しかし、これは時間差の問題ですから、今後は景気が上昇し、賃金や雇用も回復することになります。
日本経済は長かったデフレから、ようやく反転する時期に来たのです。
転換点はマイナス金利の導入
転換点となったのは、マイナス金利の導入です。
マイナス金利を導入するまでは、最低金利がゼロとなり、これより下げることができませんでした。
つまり、デフレで物価が2%下落した場合、実質金利は名目がゼロでも、実際はプラス2%(物価がゼロ%の前提)と同じことです。
ですから、実質金利でみますと、ゼロ金利は金融緩和になっていなかったのです。
このため、大企業はキャッシュをため込み、事実上の実質高金利を享受しました。
キャッシュのまま持っていると、年月の経過とともにキャッシュの価値が増す(=物価の下落で購買力が増す)という時代だったのです。
そのような時代には、何かにつけて、設備投資や雇用よりも、キャッシュをため込むことが経済的に合理的で重要、ということになります。
これが、アベノミクスが機能しなかった理由です。
しかし、マイナス金利を導入しますと、実質金利の調整が可能となります。
デフレ(物価の下落)が5%なら、金利はマイナス3%にして調整できますし、デフレが8%なら、金利はマイナス6%というように対応できるわけです。
これがゼロより下げられないと、デフレの場合、なすすべがありません。
例えば、デフレが(物価下落)が5%で、金利が0%なら、実質金利はプラス5%。高度経済成長の時期と同じような高い金利では、不況期の経済の刺激はできません。
Next: 若手正社員は一足先に景気上昇中、好景気は他世代にも波及へ